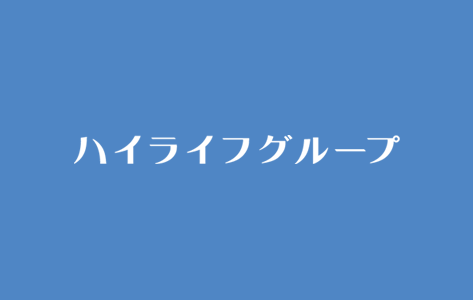「総入れ歯が外れやすい」「見た目や噛み心地に不満がある」——そんなお悩みはありませんか?近年、総入れ歯の種類や素材は大きく進化しており、選び方次第で快適さは大きく変わります。
本記事では、総入れ歯の種類や費用、選び方のポイント、よくあるトラブルまでわかりやすく解説します。ご自身に合う入れ歯を見つける第一歩として、ぜひご活用ください。
1. こんなお悩みありませんか?
「うまく噛めない」「外れそうで不安」そんな毎日を過ごしていませんか?
総入れ歯をお使いの方から、よくこのようなお悩みの声をいただきます。「しっかり噛めない」「ズレそうで、食事が楽しくない」というご相談です。
以前は問題なかったのに、ある日突然合わなくなってくることもあります。
その理由は、入れ歯だけでなく、お口の中の状態も日々変化しているからです。あごの骨が痩せたり、歯ぐきの形が変わることで、入れ歯の安定性が失われます。
「最近、左側ばかりで噛んでいる」「硬いものを避けるようになった」そんな何気ないクセが、噛み合わせのズレにつながることもあります。
また、入れ歯がわずかに動くと、あごに余計な力が加わり疲れやすくなります。「使っていれば慣れる」「我慢すればいい」——本当にそうでしょうか?
入れ歯は、日々の食事や会話を支える大切な「からだの一部」です。
不安を抱えたまま生活するより、「自分に合った入れ歯に出会うこと」で、噛むこと・話すこと・笑うことを、もう一度自然に楽しむことができるのです。
話すたびにズレる・カチカチ鳴る・違和感が取れない
入れ歯を使っているときに、「カチカチ」という音が鳴ることはありませんか?
この音の原因は、入れ歯の噛み合わせだったり、しっかり吸着していないことが考えられます。
特に総入れ歯の場合、上あごや下あごにぴったり密着していないと、話すたびに動いてしまい、音が出たり、発音がしづらくなったりします。
さらに、唾液の量が少ない方や、あごの骨が痩せている方は、入れ歯が吸着しにくく、ズレやすい傾向にあります。「口を開けたときに落ちそう」「食事中にズレる感じがある」こうした違和感は、生活の質を大きく下げてしまいます。入れ歯安定剤で一時的に抑えることも可能ですが、根本的な解決には、お口に合った精密な入れ歯が必要です。
また、長年同じ入れ歯を使い続けていると、素材がすり減り、もともとの形から少しずつ変わってしまうこともあります。「使い慣れているから大丈夫」ではなく、「今の入れ歯が本当にフィットしているかどうか」を見直すタイミングかもしれません。
「もっと自分に合った総入れ歯があるなら試してみたい」
近年では、総入れ歯の種類も色々なものがあります。「合わないのが当たり前」と思っていた方にこそ、ぜひ知ってほしいです。
たとえば、歯ぐきのやわらかさを再現したシリコン素材の入れ歯。やさしくフィットして痛みが出にくく、食事や会話のストレスを軽減します。
また、金属を使って薄く仕上げた入れ歯は、違和感が少なく、しゃべりやすさや温度の伝わり方にも優れています。さらに、近年注目されているのが、3Dスキャンを活用したデジタル入れ歯です。精密なデータで作るため、フィット感や再現性が高く、もしもの壊れた時にも複製も容易です。
自分に合う入れ歯を選ぶことで、食べる・話す・笑うという毎日が変わります。
まずは、「今の入れ歯、本当に合っている?」と立ち止まってみることから始めませんか?私たちは、一人ひとりのお口の状態やお悩みに合わせた入れ歯づくりをお手伝いしています。我慢せず、もっと自然で快適な総入れ歯を目指して、一緒に考えていきましょう。
2. 総入れ歯にはどんな種類がある?

「総入れ歯」と一言で言っても、実は素材や作り方によっていくつかの種類があります。
それぞれに特徴や費用、使い心地の違いがあり、選び方によって快適さは大きく変わります。
この章では、現在多くの歯科医院で提供されている代表的な総入れ歯について、5つのタイプに分けて、それぞれの特徴や向いている方をわかりやすく解説します。
健康保険が使える、一般的な総入れ歯(レジン床義歯)
保険診療で作られる総入れ歯は、「レジン床(しょう)義歯」と呼ばれるタイプです。入れ歯全体がプラスチック製で作られており、費用を抑えられるのが最大の特徴です。
保険が適用されるため、費用は1〜2万円程度(自己負担3割の場合)で作ることが可能です。初めて総入れ歯を作る方にも、導入しやすい選択肢といえるでしょう。
ただし、強度を保つために入れ歯がやや厚く作られており、そのぶん口の中での違和感が大きいと感じる方もいらっしゃいます。
また、プラスチック素材は経年劣化しやすく、割れたりすり減ったりすることもあります。数年に一度の作り替えや調整を前提として使用する必要があります。
「まずは保険で作ってみたい」「費用を抑えながら試してみたい」方には適していますが、見た目や快適さにこだわりたい方には物足りなさを感じることもあるかもしれません。
ぴったりフィットする自費の総入れ歯(精密義歯)
精密義歯とは、あごや口の動きに合わせて細かく調整を行い、噛み合わせや吸着力を高めた自費診療の総入れ歯です。型取りの方法から異なり、口の開閉や舌の動きに合わせて設計されるため、より自然にフィットし、外れにくく、話しやすいというメリットがあります。
「ご飯を食べていても外れない」「しゃべりやすくて疲れにくい」そんな使い心地を求める方に、非常に人気があります。
費用は30万円台後半〜80万円以上とやや高額になりますが、快適さを重視する方にとっては、それだけの価値を感じられる選択肢です。
歯科医院によっては、仮義歯の試用期間を設けるなど、じっくりと時間をかけて調整することもあります。
「市販の安定剤に頼らず、しっかりした入れ歯を作りたい」そんな方にこそおすすめできる、本格的な総入れ歯です。
薄くて違和感の少ない金属床の総入れ歯
金属床の総入れ歯は、歯ぐきに触れる部分(床)に金属を使用した入れ歯です。コバルトクロムやチタンなど、軽くて丈夫な素材が使われることが多くなっています。
レジン床と比べて薄く作ることができるため、口の中での違和感が少なく、発音がしやすくなる、あごが疲れにくいといった利点があります。
さらに、金属は熱を伝えやすいため、食事の温かさや冷たさを感じやすくなります。「食事の楽しみが戻ってきた」と話す方もいらっしゃいます。
費用はおおよそ30万円〜70万円と、やや高額ではありますが、長く快適に使いたい方にとっては、満足度の高い選択肢といえます。金属アレルギーが気になる方には、チタンなど対応素材も選べるため、安全性の面でも安心して使用することができます。
やわらかく痛みをやわらげるシリコン義歯
「入れ歯を入れると歯ぐきが痛い」「硬い素材が苦手」そんなお悩みを持つ方に人気なのが、シリコンを使った総入れ歯です。歯ぐきと接する部分にやわらかいシリコン素材を用いることで、噛んだときの衝撃をやさしく吸収し、痛みを軽減することができます。
長時間入れていても痛みが出にくく、特にあごの骨が痩せている方、入れ歯に慣れにくい方に適した設計といえるでしょう。
ただし、シリコンは毎日の丁寧な洗浄が必要です。費用は30万円〜60万円が目安となります。「痛みのせいで入れ歯を外して過ごしている」という方には、再び快適に生活する第一歩として、ぜひ検討していただきたい入れ歯です。
デジタルで管理できる3Dプリント義歯(再製作がしやすい)
近年注目されているのが、デジタル技術を活用して作る3Dプリント義歯です。お口の中を3Dスキャンし、コンピューター上で精密に設計されます。
大きな特徴は、一度データを保存しておけば、紛失や破損の際に再度同じ入れ歯を作れること。再製作がスムーズにできるため、「予備としてもう一つ欲しい」場合にも対応可能です。
また、設計の精度が高く、個人のあごの形状や噛み合わせに合った形で作成できるため、装着時の安定感や快適さにも優れています。
費用は医院によって異なりますが、20万円〜30万円台が目安とされています。
3.総入れ歯の費用はどのくらいかかる?

総入れ歯を検討するうえで、多くの方が最も気になるのが「費用」です。健康保険が使えるものから、自費で作る高機能なものまで種類はさまざまです。
しかし、ただ「高い・安い」だけで判断するのはおすすめできません。費用とともに、素材・設計・治療技術にも大きな違いがあるからです。
ここでは、総入れ歯の費用について、保険と自費のちがいをふまえながら、実際にかかる金額の目安や、選ぶときの注意点までわかりやすく解説します。
保険診療と自費診療の違い
まず知っておきたいのが、「保険診療」と「自費診療」の違いです。総入れ歯にはこの2つの枠があり、それぞれ内容と費用が大きく異なります。
■保険診療(健康保険が使える入れ歯)
・治療内容や使用できる材料が決められている
・使用する素材は主にプラスチック(レジン)
・技工費や設計も限られ、シンプルな構造になる
・自己負担は1〜3割(年齢や所得による)
費用の目安は、1万円〜2万円前後(自己負担3割の場合)です。費用を抑えたい方や、まずは入れ歯を試してみたい方には適しています。
■自費診療(保険外で自由に設計できる入れ歯)
・素材や設計、型取り方法に制限がない
・金属・シリコン・精密設計・3Dプリントなど材料が選べる
・技工士による細やかな仕上げが可能
・見た目やつけ心地など、希望に合わせた対応ができる
費用の目安は、30万円〜100万円以上になることもあります。ただし、自由度が高く、患者に合わせた細かな調整が可能という大きな魅力があります。
自費の総入れ歯が高額な理由とは?
自費の総入れ歯は、なぜ保険に比べて費用が高くなるのでしょうか?理由はいくつかありますが、主に次の3点が挙げられます。
1.素材の質が異なる
自費の入れ歯では、薄くて丈夫な金属や、やわらかいシリコン素材が使用できます。
2.設計や製作の工程が多い
患者の口に合わせて、噛み合わせやあごの動きまで細かく調整します。その分、診察回数や製作にかける時間が長くなり、技術料も反映されます。
3.技工士による高精度な仕上げ
熟練した歯科技工士が、オーダーメイドで丁寧に製作します。一人ひとりに合わせた細かな設計が、快適な装着感につながります。
このように、費用が高いのには明確な理由があり、そのぶん使い心地や満足度に差が出やすいのが自費の入れ歯です。
医院によって異なる料金体系。まずは相談してみよう
自費診療の入れ歯は、自由度が高い反面、医院ごとに費用が異なります。同じ金属床の入れ歯でも、設計の違いや調整の回数で価格が変わることがあります。
また、費用に「調整料」「再診料」「保証期間」などが含まれるかどうかも、医院ごとに異なるため、あらかじめ確認しておくことが大切です。
医院によっては、分割払いや医療ローンに対応している場合もあります。「費用が心配で相談しづらい」と思わずに、まずは遠慮なく聞いてみましょう。
最近では、カウンセリングや相談を無料で行っている医院も増えています。不安を抱えたままにせず、まずは話を聞いてみることが、良い入れ歯選びの第一歩です。
4.自分に合った総入れ歯を選ぶための3つの視点
総入れ歯は、ただ歯が入っていればいいというものではありません。見た目、噛みやすさ、つけ心地など、ご自身にとって大切なポイントは人それぞれです。
ここでは、総入れ歯選びで失敗しないために意識したい「3つの視点」をご紹介します。どの視点がご自身に当てはまるかを考えながら読み進めていただくと、判断しやすくなります。
自然な見た目に仕上げたい方へ(歯の形・歯ぐきの色・表情との調和)
「入れ歯だと気づかれたくない」「人前でも自然に笑いたい」そんな方にとって、入れ歯の見た目はとても重要なポイントです。
総入れ歯であっても、歯の並び方や歯ぐきの色合いを工夫することで、本物の歯のように自然な仕上がりに近づけることができます。
特に自費診療で作られる義歯は、歯の形や大きさなども個別に調整することが可能です。
また、歯ぐき部分の色も、ご自身の肌や唇の色に合わせて着色できることもあり、「人工物感の少ない口元」を目指す方に適しています。
さらに、顔全体とのバランスも大切な視点です。入れ歯の厚みや歯の位置によって、表情が変わることもあるからです。たとえば「以前よりほうれい線が目立ってきた」と感じる方も、入れ歯の調整によって、口元がふっくらと自然な印象に変わることがあります。
「入れ歯=老けて見える」というイメージを持つ方も多いですが、しっかり設計された入れ歯なら、表情が明るく若々しく見えることもあるのです。
噛みやすさ・話しやすさなど機能性を重視したい方へ
「外れやすくて、しっかり噛めない」「発音がはっきりしない」そんな日常のストレスは、総入れ歯の設計や素材によって改善できることがあります。
特に食事中の噛みにくさは、吸着力やかみ合わせの精度に大きく関係しています。自費でしっかり作ったの入れ歯は、歯ぐきやあごにぴったり合うよう設計されており、噛む力がしっかり伝わるため、食べ物をしっかりと咀嚼できます。
また、金属床の入れ歯は厚みが少なく、発音がしやすいという特徴もあります。また他の自費の入れ歯でも一人ひとりのお口にピッタリ合うように製作しますので、舌の動きがスムーズになり、「サ行」や「タ行」がはっきりと出やすくなったりします。「口を開けたときに入れ歯が落ちそうになる」「しゃべるたびに動く」このようなトラブルも、吸着設計の見直しや素材の変更で改善されることがあります。
さらに、噛み合わせがしっかり合っていないと、あごに余計な力がかかり、肩こり・頭痛・顎関節症など、全身の不調につながることもあるのです。
機能面を重視する方には、あごの動きや筋肉の状態を見ながら作る義歯をおすすめします。噛む・話す・笑うを、より自然に行えることが、毎日の快適さにつながります。
長く快適に使える入れ歯を選びたい方へ
総入れ歯は、「一度作ればずっと使える」というものではありません。
時間の経過とともに、あごの骨が痩せたり、歯ぐきの形が変わることで、はじめはぴったりだった入れ歯も、徐々に合わなくなってくるのが一般的です。
そのため、「長く快適に使いたい」と考える方ほど、メンテナンスのしやすさや再製作のしやすさを意識して選ぶことが大切です。
たとえば、金属床の入れ歯は強度が高く、変形しにくいため長く使いやすい素材です。
また、3Dプリント義歯はデジタルデータが保存されているため、万が一の破損や紛失時でも、同じ形の入れ歯を再製作しやすいというメリットがあります。
シリコン義歯のように、やわらかく快適な素材を使ったものでも、貼り替えを前提にしておくことで、長く使用することができます。
そして、何より大切なのが定期的な歯科でのチェックと調整です。
入れ歯の状態だけでなく、あごや粘膜、舌の動きなども確認しながら、
「今の自分に合っているかどうか」を定期的に見直していくことが大切です。
「痛くなってから行く」ではなく、「違和感が出る前に相談する」それが、入れ歯と長く付き合うための最大のコツです。また、材料だけで解消するものではなく、歯科医師と技工士の技術力がとても重要だということも忘れてはいけません。
5. 総入れ歯でよくあるトラブルと、その対策

「せっかく入れ歯を作ったのに、うまく使いこなせない」そんな声を実際の診療でもよく耳にします。
総入れ歯は、歯が一本も残っていないお口に装着するため、
あごの骨や歯ぐきにぴったり合っているかどうかが重要になります。
しかし、使い始めてから時間が経つにつれ、思わぬトラブルや不快感が出てくることもあります。
ここでは、総入れ歯にありがちな代表的なトラブルと、その原因・対策についてわかりやすく解説していきます。
入れ歯が外れやすい・吸着しない・すぐに落ちる
総入れ歯の大きな役割のひとつが、「吸着(きゅうちゃく)」です。これは、上あごや下あごにぴたっとくっついて動かない状態を指します。しかし、「話すときに外れそうになる」「口を開けると落ちてしまう」こうしたお悩みは、吸着がうまくいっていないサインかもしれません。
原因の一つは、あごの骨の変化です。歯を失うと、あごの骨は少しずつ痩せていきます。それに合わせて入れ歯が合わなくなり、隙間ができてしまうのです。
また、元々の設計が合っていない場合や、経年によって入れ歯がすり減ってしまうことも関係しています。
【対策】
・入れ歯の裏側を調整する「リベース(裏打ち)」で吸着力を高める
・状態に応じて作り直しも検討。長年使っている入れ歯ほど要注意
・安定剤の使用は一時的な手段。根本改善にはならないことを理解しておく
・シリコン義歯で吸着力を高める
痛みやあたりが出て、長時間使えない
「数時間つけていると、歯ぐきがジンジンしてくる」
「食事のたびに、ある一か所だけが痛む」
このような症状も、総入れ歯ではよくあるトラブルの一つです。
原因として多いのは、入れ歯の一部が粘膜に強く当たっていることです。
特に、歯ぐきの状態が変化したり、骨の形に合わせた調整が不十分だった場合に起こります。
また、硬い食べ物を噛んだときに痛みが出る場合は、入れ歯の厚みやかみ合わせのバランスに問題があることもあります。
【対策】
・あたっている部分をピンポイントで削ることで痛みを軽減
・食べるときの力のかかり方を調整することで、症状が改善することもある
・「我慢すれば慣れる」は禁物。早めに歯科医師に相談することが大切
食事がしにくい・発音しづらい・カチカチ音がする
「うまく噛めなくて、食べこぼしてしまう」「話すと入れ歯が動いて、発音がはっきりしない」「しゃべるたびにカチカチ音がして気になる」これらも総入れ歯でよくある日常的なお悩みです。
噛みにくさは、かみ合わせのずれや吸着力の低下が原因であることが多いです。
また、入れ歯の素材が厚すぎると、舌の動きが妨げられ、発音に支障をきたします。「カチカチ」という音は、上下の入れ歯が強く当たっている証拠です。長期間この状態が続くと、入れ歯が割れる原因にもなりかねません。
【対策】
・噛み合わせの調整を行うことで、噛みやすさ・発音の改善が見込める
定期的な調整と、口の変化への対応が快適さのカギ
入れ歯は、「作って終わり」ではありません。お口の中は年齢とともに変化するため、定期的なメンテナンスが不可欠です。
あごの骨がやせると、少しずつ入れ歯が合わなくなってきます。それに気づかず使い続けると、痛みやトラブルの原因になることもあります。また、入れ歯自体も少しずつすり減ったり、変形していくことがあります。こうした小さな変化を見逃さないためには、定期的なチェックが何より大切です。
【対策】
・半年に一度は歯科医院で入れ歯の状態をチェックしてもらう
・「痛みがない=問題がない」とは限らない。予防の視点が大切
・お口の状態に合った入れ歯を、その都度調整して使い続ける
6.まとめ
総入れ歯は、素材や設計によって見た目や噛み心地が大きく異なります。「今の入れ歯が合わない」「もっと快適な方法があるかも」と感じている方こそ、正しい情報を知った上で、自分に合った入れ歯を選ぶことが大切です。お悩みの際は、どうぞお気軽に当院までご相談ください。あなたに合う入れ歯づくりを丁寧にお手伝いします。