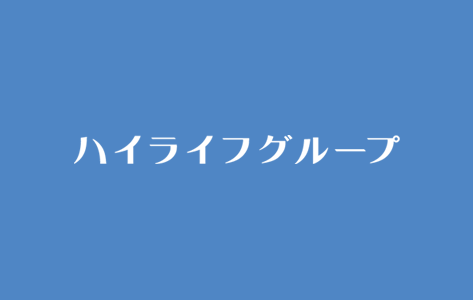「入れ歯でうまく噛めない」「食事が楽しめない」——そんなお悩みは多くの方に共通しています。
この記事では、入れ歯が食べにくい原因と改善のポイントを詳しく解説します。
1. 入れ歯で食べづらい…こんな悩みありませんか?

「噛みにくい・外れやすい・痛い」などの代表的な声
「入れ歯でうまく噛めない」「食事中にずれてしまう」「噛むと痛む」——。
こうしたお悩みは、入れ歯を使っている方の中でも非常に多く聞かれます。
とくに、50代〜70代の方にとって、毎日の食事は健康維持や楽しみの源。
にもかかわらず、入れ歯が原因で食べたいものが思うように食べられないと、生活の質は大きく下がってしまいます。
歯ぐきに入れ歯が当たって痛む、しっかり吸いつかずに動いてしまう、咀嚼(そしゃく)中に「パカパカ」と音が鳴る……。
これらの症状は、入れ歯の形やかみ合わせが、今のお口の状態に合っていない可能性があります。無理に慣れようと頑張る方もいますが、根本がずれていれば、症状は改善しません。
実は多くの方が抱えている入れ歯の食事トラブル
入れ歯の悩みは決して一部の人だけの問題ではありません。
厚生労働省の調査でも、70代の約4割が総義歯(上下どちらかが全部義歯)を使っており、
その多くが「硬いものが噛みにくい」「すぐに外れる」といった違和感を抱えています。
中でも問題となるのが、「なんとなく使えているから」と相談せずに放置してしまうケースです。
違和感があっても慣れでごまかしていると、知らず知らずのうちにかむ力が落ち、飲み込みにも悪影響が出ます。
また、片側ばかりで噛んだり、やわらかい物しか選ばなくなったりと、日々の食生活にも偏りが生じていきます。
これは、高齢期の栄養状態や誤嚥(ごえん)性肺炎のリスクにも直結するため、たかが「食べにくい」とあなどれない問題です。
食べにくさを我慢し続けるリスクとは
入れ歯が合っていないまま使い続けると、歯ぐきの粘膜に繰り返し負担がかかり、炎症やただれを引き起こします。
その結果、余計に入れ歯が動きやすくなり、痛みをかばうことであごの動かし方にもクセがついてしまいます。
こうなると、「合わない入れ歯→食べにくい→噛まない→口の筋肉が衰える→さらに合わない」という悪循環に陥ってしまうのです。
さらに、入れ歯が不安定な状態では、人と話すこと自体に抵抗を感じるようになり、外出や人付き合いを避けるようになる方もいます。
入れ歯の問題は、単なる口の中だけのことではなく、「健康」「食事」「人間関係」すべてに影響を及ぼす生活課題です。
とはいえ、原因は一つではありません。入れ歯の形や素材、支え方、かみ合わせのバランス、さらには作った時と現在のあごの状態の違いまで、複雑に関係しています。
だからこそ、「今の入れ歯は本当に自分に合っているのか?」という視点で、見直すことがとても大切です。
2. 噛めない・痛い入れ歯のまま使い続けるとどうなる?
噛み合わせがずれている
入れ歯で噛みにくくなる原因として、まず見逃せないのが「噛み合わせ」のずれです。
かみ合わせが正しくないと、力が左右どちらかに偏ったり、かんだときに痛みを感じたりします。
とくに、あごの位置が入れ歯に合っていないと、上下の歯がうまくかみ合わず、食べ物をこぼしたり、すりつぶせなかったりします。
この状態が続くと、あごの関節や筋肉にも負担がかかり、肩こりや頭痛につながることもあります。
入れ歯が歯ぐきに合っていない・浮き上がる
入れ歯は、歯ぐき(粘膜)にのせて使うため、ぴったりと吸い付くように合っていないと安定しません。
しかし、歯を失ったあごの骨は、少しずつやせていきます。すると、最初に作った入れ歯が、時間とともに歯ぐきに合わなくなり、食事中に浮き上がったり、カタついたりするようになるのです。
特に、総入れ歯を使っている方はこの傾向が強く、吸着力が弱まると、入れ歯が外れそうになる不安から、食べること自体が苦痛になります。
噛む力が伝わりにくい構造になっている
入れ歯は、天然の歯のようにあごの骨にしっかり固定されているわけではありません。
そのため、力をかけると歯ぐきが痛んだり、入れ歯が沈み込んだりして、十分な力が伝わらないことがあります。
結果として、食べ物がよくかめず、胃や腸に負担がかかるケースも少なくありません。
食べ物が詰まりやすく、痛みや不快感がある
入れ歯と歯ぐきの間に隙間があると、そこに食べ物が入り込みやすくなります。
とくに繊維質の野菜やご飯粒などが挟まると、噛むたびに歯ぐきが押されて痛みを感じることがあります。
これは、粘膜がこすれたり、圧迫されたりすることで起こる炎症の一種です。
また、異物感が強くなると、食事中に無意識に舌で押し返したり、入れ歯を外したくなったりする方もおられます。
食事中に入れ歯がズレて会話や飲み込みに支障が出る
食べ物をかんでいる途中で入れ歯がずれると、思わず口を閉じて飲み込んでしまうことがあります。
これは、かむ動作がスムーズに行えないことで、飲み込みにも悪影響を与える典型的な例です。
また、唇の動きや舌の位置が不安定になるため、会話中に「カチカチ」と音が鳴ったり、入れ歯が落ちそうになる場面も出てきます。
このような状態は、心理的にも大きなストレスとなり、外食や人前での食事を避けるきっかけになります。
3. 噛める入れ歯を作るために大切なポイント

噛み方のクセ・生活習慣に合わせた設計が必要
入れ歯づくりは、ただ型を取って「形を整える」だけでは成り立ちません。
一人ひとりのあごの動かし方、噛むときの力のかけ方、左右どちらでよく噛むかなど、細かい「噛みグセ」や日常の習慣を読み取ることが重要です。
例えば、片側ばかりで噛むクセがある方に、左右対称の設計で作ってしまうと、噛んだときにうまく力が伝わらず、入れ歯がズレる原因になります。
また、歯ぎしりや食いしばりのある方は、強い力に耐えられるような厚みや形状の工夫も必要です。
患者さんの生活背景まで含めて考えることが、快適に噛める入れ歯をつくる第一歩です。
技術・経験のある歯科医師と技工士の連携力
入れ歯治療は、歯科医師一人の力だけでは完成しません。
設計した入れ歯を実際に形にするのは、歯科技工士の仕事です。どれだけ精密に型を取り、計測しても、その情報を正しく技工士に伝え、綿密に連携して仕上げなければ、良い入れ歯にはなりません。
経験豊富な歯科医師は、技工士とのやり取りの中で、「患者さんの表情筋の動き」「発音のしやすさ」「あごの開閉角度」などを伝え、細部にまでこだわって指示を出します。
逆に、経験や連携が浅いと、入れ歯の精度は下がり、「なんとなく噛めるけれど、痛い」「外れにくいけれど、噛みづらい」といった中途半端な仕上がりになります。
噛める入れ歯には、医師と技工士の“チームの力”が不可欠です。
治療後の「調整とサポート」で完成度が決まる
入れ歯は「作って終わり」ではありません。
装着後には、数回にわたって噛み合わせの微調整を行い、必要に応じて形や厚みを整えていきます。この過程を丁寧に行うことで、食事中のズレや痛みを解消し、自然な噛み心地に近づけることができます。
また、長期間快適に使うためには、年に1〜2回の定期点検も欠かせません。あごの骨や粘膜は年齢とともに変化するため、それに合わせて入れ歯も調整が必要になります。
「治療後のフォロー体制」が整っているかどうかは、医院選びでも注目すべき重要なポイントです。
4. 「食べやすさ」で選ぶ入れ歯素材と設計の考え方
自費・保険の入れ歯で何が違う?
入れ歯には、健康保険が適用されるものと、自費で作るものがあります。
どちらも「噛む」という目的は同じですが、素材の自由度や設計の細かさに大きな差があります。
保険の入れ歯は、あくまで「最低限の機能回復」を目的として作られており、使用できる素材も限られています。
多くは、プラスチック製の土台と既製の人工歯を使って作られ、厚みがあり、割れにくさを重視した設計になります。
一方、自費の入れ歯は、使用できる素材や設計に制限がなく、患者さん一人ひとりの噛み方・話し方・見た目の希望にまで合わせた精密な調整が可能です。そのため、より「噛みやすく」「目立ちにくく」「違和感の少ない」入れ歯に仕上げられるのが特長です。
お口の状態とご希望に合った素材選びのコツ
入れ歯の素材選びは、ただ「見た目」や「費用」だけで決めてはいけません。
たとえば、あごの骨が大きくやせている方は、柔らかい素材で痛みを吸収する工夫が必要です。一方で、硬いものをしっかり噛みたい方には、力が伝わりやすく安定感のある設計が適しています。
また、「できるだけ薄く違和感の少ない入れ歯にしたい」「金属の見える部分をなくしたい」といったご希望も、素材によって実現の可否が変わります。
重要なのは、今のお口の状態と生活スタイル、ご本人の希望をすべてふまえたうえで素材や形を選ぶことです。
そのためには、歯科医師との丁寧な相談と、複数の選択肢を提示してくれる体制がある医院を選ぶことが大切です。
金属床・シリコーン・ノンクラスプ…各素材の特徴
代表的な入れ歯の素材には、以下のような種類があります。
・金属床義歯
土台の部分が金属でできており、薄くて丈夫。
熱伝導性が高く、食べ物の温度を感じやすい。
強度があり、発音もしやすいが、金属アレルギーの方はチタンにするなどの注意が必要。
・シリコーン義歯
歯ぐきに接する面にやわらかい素材(シリコーン)を使用。
痛みが出やすい方、あごがやせている方に適している。
クッション性が高く、装着時の安心感がある。
・ノンクラスプ義歯
金属のバネがなく、見た目が自然。
部分入れ歯に多く用いられ、笑ったときに金具が見えるのが気になる方に人気。
ただし、噛む力の伝達性はやや劣ることもある。
これらはそれぞれにメリット・注意点があり、どれが「正解」というわけではありません。
者さんのお口の状態と生活の優先順位によって最適な組み合わせを選ぶことが、快適な入れ歯づくりには不可欠です。
5. 入れ歯が食べにくいと感じたときの対処法
我慢せずに歯科医院で相談を
「慣れればそのうちよくなるだろう」「年齢のせいだから仕方ない」と、違和感や噛みにくさを長く放置している方が多くいらっしゃいます。
しかし、合っていない入れ歯を無理に使い続けることで、歯ぐきが傷ついたり、噛み合わせが悪化したりと、状況はむしろ悪くなることがあります。
入れ歯が食事中にずれたり、噛むと痛みが出るようであれば、それは明らかに「調整や見直しが必要なサイン」です。
また、以前は問題なく使えていた入れ歯でも、時間の経過とともに歯ぐきやあごの形が変化するため、再びの調整が必要になることは珍しくありません。
違和感を感じた段階で、早めに歯科医院に相談することが、快適な入れ歯生活への第一歩です。
補綴専門医など、入れ歯に詳しい歯科医師を探す
入れ歯の悩みは、どこの歯科医院でも解決できるとは限りません。
とくに「何度調整しても噛みにくい」「作り直しても納得できない」というケースでは、入れ歯の専門的な知識と経験がある歯科医師に相談することが大切です。
「食べやすい入れ歯を本気でつくる医院」を見極めるには、歯科医師の経歴、症例実績、院内歯科技工士、治療方針などをホームページなどで確認すると良いでしょう。
調整・修理だけで改善するケースも多い
「新しい入れ歯を作らないとダメかもしれない」と不安になる方も多いですが、必ずしも作り直しが必要とは限りません。
実際には、現在使っている入れ歯に数回の調整を加えるだけで、驚くほど快適に使えるようになるケースも多くあります。
たとえば、わずかな高さの調整で噛みやすくなったり、歯ぐきとのすき間を埋める修正をすることで安定性が改善されたりします。
また、修理や補強を施すことで、今の入れ歯を継続して使えるようにすることも可能です。
大切なのは、「我慢を続ける」よりも、「一度相談して、今の状態を客観的に見てもらう」こと。
合わない入れ歯に慣れようとする前に、**合うように整えることができるか**を検討してみてください。
6. よくある質問(FAQ)
入れ歯が食べにくいのは慣れの問題ですか?
一部は慣れも関係しますが、根本的な原因がある場合は調整が必要です。
とくに「痛みがある」「外れやすい」「噛んでもすりつぶせない」などの症状は、入れ歯の設計や噛み合わせに問題がある可能性が高く、放置しても改善しません。
歯科医院で診てもらうことで、明確な原因と対応方法が見えてきます。
どのくらいの頻度で入れ歯の調整は必要ですか?
一般的には半年〜1年に1回が目安です。
ただし、使い始めて間もない時期は、数回にわたる細かい調整が必要になります。
また、痛み・ぐらつき・噛みにくさなどの不調を感じたときは、期間にかかわらず早めに調整を受けることをおすすめします。
自費の入れ歯にすれば確実に噛めるようになりますか?
自費だから必ず噛めるというわけではありません。
ただし、自由な設計や素材が使えるため、「より自分に合った入れ歯」を追求することができます。
大切なのは、患者さんのお口に合った設計を、技術力のある歯科医師と技工士が手がけることです。
素材や費用だけで判断せず、治療の内容と体制をよく確認しましょう。
どんな歯科医院に相談すればよいですか?
入れ歯治療に力を入れており、補綴に詳しい歯科医師が在籍している医院を選ぶのがおすすめです。
ホームページなどで「入れ歯の専門治療」や「補綴歯科」の実績が紹介されているかを確認しましょう。
また、実際の治療例や患者さんの声が掲載されている医院は、対応に自信を持っている証拠です。
入れ歯は治療後の調整も重要なので、長く付き合える医院かどうかも大切な視点です。
7. まとめ
入れ歯の噛みにくさは、我慢せず相談することで改善できる可能性があります。
ご自身に合った入れ歯で、毎日の食事をもう一度楽しめるようにしましょう。